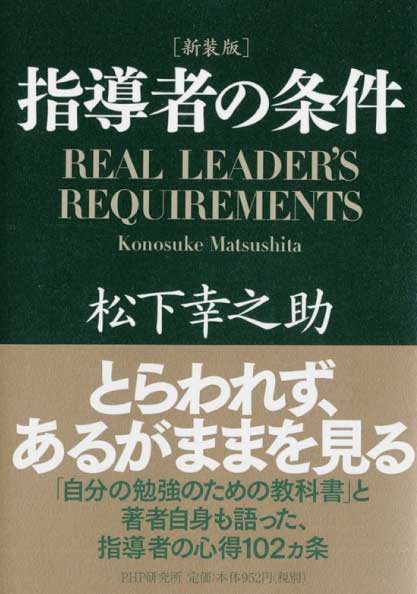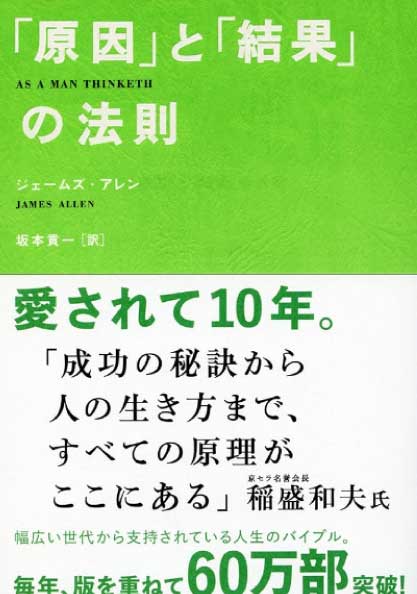01
- 樋田 京子先生
- 北海道大学歯学研究院教授
先人たちの努力の上にある今の生活を
当たり前だと思わない
LILAS
Leaders for people with Innovation,
Liberty and AmbitionS.
フロントランナーとして活躍している女性リーダー(Leader)を紹介する女性研究者インタビューシリーズLILAS。リラはフランス語で札幌の花としても知られるライラック(Lilac)を意味します。 インタビューの内容から着想を得た植物のアレンジメントとともに、植物の持つ力強さやしなやかさ、多様性などのメッセージを媒介させながら、オリジナルインタビューシリーズとして発信していきます。
- 01
-
第一回は歯学研究院の樋田京子さん。歯学部を卒業後に結婚。臨床医として勤務したのち大学院進学、博士号取得後も産休をはさみながら臨床医として働いていましたが、夫の留学を機に渡米。アメリカで子育てしながらポスドクとして研究する生活を送り、帰国後は北大で研究者としてのキャリアを歩んでいます。子育てで時間的制約があったことから、助教時代から研究室メンバーがそれぞれ納得して研究を進めていくことが研究室として成果を挙げることにつながると常に意識し、自分のふるまいやメンバーとのコミュニケーションについて試行錯誤しながら自分なりのマネジメント方法を築いてきたという樋田さん。その考え方からTipsまでご紹介します。

周りの研究室では夜遅くまで教員が
実験に付き合ってあげられる環境がある。
どうすればメンバーは同じ方向を
向いてくれるだろう
子育て期からはじまった研究室運営。限られた時間の中で研究を進めるために心がけていたことはありますか?
助教の頃から試行錯誤の連続でした。子育てで帰らなければいけない時間のリミットがあり、学生時代のように夜遅くまで自分の時間をすべて研究に使える状況ではありませんでした。今思えば必要以上にディスアドバンテージ(不利)に感じていたのかもしれませんが、周りの研究室では夜遅くまで教員が実験に付き合ってあげられる環境があるのは事実です。どうすれば研究室のメンバーがその環境を受け入れて同じ方向を向いて研究を進められるか常に考えていました。
特に特任准教授時代の9年間は、人件費、賃料、研究費など自分で捻出しなければならず、自分自身の雇用も年度ごとの更新と不安定。成果が上がらないと外部資金の獲得につながらず、研究室が潰れてしまうという危機感を常に持っていました。研究室が潰れてしまうと自分自身のみならず、スタッフの雇用や大学院生の研究が継続できなくなり、学位取得も危ぶまれるという責任を背負っているので、とにかく頑張るという選択しかありませんでした。
成果を上げていくには自分一人ががむしゃらに頑張ったところで限界があります。やはりチームでなければならない。研究室のメンバーが一丸となって研究を進めていくことが重要という思いが強まったのもこの時期です。
物理的にいる時間は短くても、ラボにいる間のコミュニケーションは密に
具体的にはどのような実践をしていたのでしょうか
研究室にいる時間の中で使える時間は可能な限り研究室のメンバーとのコミュニケーションに費やしていました。文献を読んだり実験ノートを作ったりというような帰宅後にできることは後回しにして、物理的にラボにいる時間は短くても、コミュニケーションが密になるように時間配分をしていました。
コミュニケーションの方法も一様ではなく、その時々のメンバーによってアレンジするなど、一人一人にあった形を常に模索して「気にかけているよ」という態度を見せることを心がけていました。日中に提出されたデータに対するフィードバックを帰宅後に子どもがお風呂に入っている間にメールで返す、などということをしていると、翌日に返すよりも半日研究が進むという実感がありました。研究の場なので時にはラボミーティングなどで厳しいことを言うこともありましたが、その後にフォローを入れたり、お互いに失敗を引きずらないように意識していました。
また、家に研究室メンバーを招いてBBQパーティーを開いて、家族ぐるみで交流するということもしていました。子育て期は子どもの体調不良などで急な休みを取らなければいけないこともあります。お互い顔を知っていると「子どもが体調不良で…」というと、お互い親身に心配しあえることもありました。家族にも研究室のメンバーにも自分のやりたいこと、やらなければならないことを理解してもらいたいという気持ちが強かったので、プライベートとの線引きはあまりせずに、積極的に交流する場を作っていました。研究以外の場面で交流し、それぞれの考え方や事情を理解するのはとても大切だと思っています。交流を深めるために夜の飲み会を開くという研究室も多いと思いますが、私にはそれができなかったので、数か月に一回の全員が揃うようなラボミーティングの際に昼食を手配してみんなで食べながらざっくばらんに話す機会をつくったりもしました。そういうことを実践していくと一人一人のモチベーションが上がったり、研究室のまとまりが良くなる、という効果が見えてきて研究も前進したように思います。大事なのは一人一人の納得感だと思ったので、一緒に頑張ってくれる環境や体制をどうやったら作れるのか考えていった結果、いろいろな機会を捉えて交流できる場を作ることを実践していました。

大変な時でも口角は常に上げておく
そのような工夫をしているロールモデルがいたのでしょうか
当時は身近に自分と同じ境遇のロールモデルはいませんでしたが、助教時代のボスである教授からこれまで色々なサポートやアドバイスをいただきました。特に「君には部下や院生がいるんだから、大変な時でも口角を常に上げておきなさい」という言葉は今も実践しています。日々、色々な不安なことがあって、朝大学に向かいながらそれについて考えていることもありますが、着いたら笑顔で、時には表情を作ってでも研究室に入って行くように心がけています。自分がどうありたいか、セルフプロデュースの力をつけていくことも重要だと思います。
また、学会や研究会などで同じ年代の研究者と交流したときに、子育てとの両立や介護の問題などそれぞれが実は個別の事情を抱えながら研究を進めているということがわかり、それも励みになっています。同じ分野の高名な先生の苦労話も耳にすることがあり「こんなにすごい先生でも苦労されているのだ」と思うと、自分もまだまだ頑張れるというという気になりました。周りに男性の研究室主宰者が多い状況で自分も研究室主宰者として奮闘している時期だったので、自分が抱える問題に対する直接的な解決にはならなくても、そのような存在があるだけで勇気づけられていましたね。
自分自身がマイノリティだったアメリカでの経験が意識変容に
研究室を運営する中でダイバーシティを意識することはありましたか?
アメリカでの経験がとても大きいです。双子の子どもが1歳のときに夫の留学に同行して家族でアメリカに行き、そこでは私自身がアジア人で女性、というまさにマイノリティでした。研究員として所属した大学では他にも留学生がいる環境で差別はあまりありませんでしたが、日々の生活では買い物や郵便局で差別と思われるようなことを受けたこともありました。私だけでなく子どもが通っている保育園でも「アジア人だからこういう対応なんじゃないか?」と思うようなことがあり何度か園を変えたりと様々な経験をしてきました。
しかし、もしかしたら相手は差別という意識でなくて不愛想だったりそういう個々人のキャラクターだったのかもしれません。その真意はわかりませんが、マイノリティーの目線だと、マイノリティーであるが故に受けた行動なのかもしれないと思ってしまう、ということを学びました。帰国してからは自分の行動にそういった差別と受け取られるような態度がないか、より気にするようになりました。
アメリカでは女性研究者も多く、日本の状況を話すと「アメリカも少し前までは同じような状況だった。日本も一世代待てば良くなるよ」と言われましたが、20年ほど経ち、一世代を待たずともDEIへの意識が高まっていて今まさにその時期にきていると思います。
特任准教授時代は1年更新という立場もあり、何か組織や制度に対して思うことがあっても飲み込んできた言葉が多くありました。ですが、教授となった今だからできることはたくさんあると思っています。私たちが経験してきた苦労を下の世代の人たちがしなくてもいいように制度の整備や具体的な課題の吸い上げなど、できることは何でもしていきたいです。

先人たちの努力の上にある今の生活を
当たり前だと思わない
教授となった今、どのようなビジョンをお持ちですか?
研究面では、臨床につながる結果を出すことが一つの目標です。そして教科書に載るような新しい発見をしていくことも目指しています。
私は血管研究をやってきたのですが、新型コロナウイルス感染症を機に感染症研究との融合も起こり、少し前までは予想していなかったような新たな血管研究が広がってきました。また、人獣共通感染症国際共同研究所との共同研究も始まって数年経ちますが、これまで歯学部の中だけで行ってきた研究と他分野の研究が融合することで研究の新たな可能性が見つかっています。そのことで大学院生たちも刺激を受け、研究に対する意識やモチベーションにもいい影響がでていると思います。
大学運営にも関わるようになり、より良い時代を作っていくために世の中の環境整備に関わっていきたいという気持ちが強くなりました。学術会議でもDEIの委員会に参画しているので、北大に限らず学術界全体からより良い方向へ変えていくために発信していきたいと思っています。こう思えるのは、やはりアメリカで言われた「日本も一世代待てば良くなるよ」という言葉が大きいです。アメリカでも女性が活躍できる世の中になるまで尽力したたくさんの先人たちがいました。その上に享受している今の権利や生活だと思うからこそ、これが当たり前と思わずに自分も頑張りたいと思えるのです。

来たチャンスには迷わず挑戦
これから上位職を目指す研究者の人たちへメッセージをお願いします
女性も男性も問わず、来たチャンスには迷わず挑戦してください。迷ってあきらめるのではなく、とりあえずやってみることがとても大事です。活躍されている研究者を見ると、自分はこのようにはなれない、とかできないと思うこともあると思います。ですが、最初からその立場で100%できる人はいません。すごいと思う研究者だって、これまで色々な失敗やそれを乗り越える試行錯誤をしてきています。“立場が人を作っていく”という言葉があるように「私にはできないかもしれない」と思うことがあっても、もしチャンスがあるならば勇気を持って進んでもらいたいです。
まだ経験してないことを最初から諦めるよりも、たとえやってみてだめだった、という結果になったとしても挑戦したほうがいいと思います。研究に限らず、何でも同じことが言えて、子育てでも最初から完璧にできる人はいないです。「子どもが一歳になったら親も一歳」というように経験していくことで育っていきますよね。そうして進んでいく背中を見ながら皆さんの下の世代が育っていく、そういう循環の中にいるということを意識していただきたいです。
LILAS
Library
「夫が読んでいた本で、マネジメントを試行錯誤しているときに家の本棚から手に取り、どうすればメンバーと信頼関係を築けるかということを考えていた助教〜特任准教授時代に折に触れて読み返していました」
LILAS
Plant
アメリカ留学から着想を得たモクレンを中心にキャリアをなぞるだけではわからない葛藤や困難をイメージし、選びました。

-
ハクモクレン(白木蓮)
学名:Magnolia denudata 科名・属名:モクレン科モクレン属
- 札幌、アメリカ、見上げるとそばにいた樹木として。
-
フリチラリア
学名:Fritillaria persica 科名・属名:ユリ科バイモ属
- 北大構内に咲くクロユリ(黒百合)もユリ科バイモ属。インタビューと撮影が行われた3月、雪の下で咲く時期を待っている花にひとつひとつクリアしていく姿を重ねる。
-
アセビ(馬酔木)
学名:Pieris japonica 科名・属名:ツツジ科アセビ属
- 含まれる毒の成分で馬が食べると酔っ払ったようになることからついた名前。春の季語のひとつ。
LILASは北海道大学創基150周年事業です。北海道大学は2026年に創基150周年を迎えます。