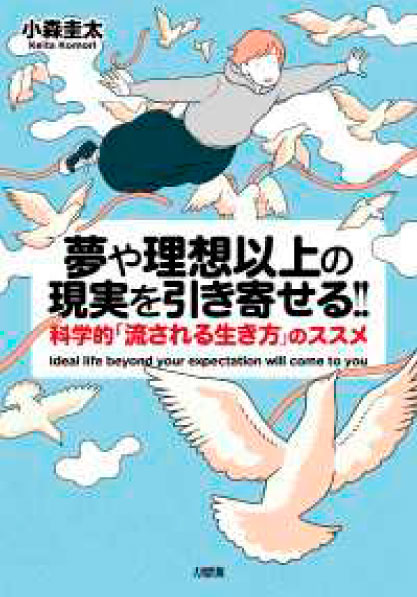06
- 池田 敦子先生
- 北海道大学保健科学研究院教授
人生は思い通りにいかないことの方が多い
でも新しい波に乗れば、
思いがけない世界が広がる
LILAS
Leaders for people with Innovation,
Liberty and AmbitionS.
フロントランナーとして活躍している女性リーダー(Leader)を紹介する女性研究者インタビューシリーズLILAS。リラはフランス語で札幌の花としても知られるライラック(Lilac)を意味します。 インタビューの内容から着想を得た植物のアレンジメントとともに、植物の持つ力強さやしなやかさ、多様性などのメッセージを媒介させながら、オリジナルインタビューシリーズとして発信していきます。
- 06
-
第六回は保健科学研究院の池田敦子さん。池田さんは、製薬会社での勤務や海外生活を経て北大大学院に進学し、環境疫学の道を歩んできました。保健科学研究院へ異動し、自身の研究室を立ち上げてからは、学生の育成や研究室運営に日々取り組んでいます。「人の健康に貢献したい」という思いを原点に、研究分野や社会、そして大学への貢献についてどのように考えているのかを伺いました。

ヒトの集団を対象に研究を進める学問、疫学との出会い
研究者としてのキャリアはどのようにスタートしましたか
大学で生物工学を学び、学部卒業後は製薬会社で10年近く働いていました。家庭の事情でシンガポールに行くことになり退職し、そこで趣味でアロマセラピーを学びはじめました。インストラクターの資格も取り、人に教えるようになったときに「本には『この精油は○○に効果がある』と書かれているが、それはヒトで確かめられたのだろうか」という疑問を持つようになりました。
帰国後、ヒトに効くことを確かめるにはどうしたらいいのだろう、という話を前職の上司にしたところ「池田さん、それなら疫学を学びなさい」と勧められて初めて疫学という学問を知りました。ヒトの集団を対象に研究を進める学問だと知り、自分の関心にぴったりだと感じ、北大大学院に進学し、疫学の道を歩み始めました。
現在はどのような研究をされているのですか
私が主に進めている出生コホート研究(疾病とその要因との関連を長期間に渡って探る調査手法)では、胎児期から幼少期の環境を調査しておき、その後、子どもの体格や疾患などの健康状況が明らかになってから、その原因となる環境を明らかにします。例えばアンケートの結果から「自宅の窓が結露する家庭では、喘息症状がある子どもが多い」など、たくさんの人に調査に協力してもらうことで統計的に傾向が見えてきます。他には、室内環境と居住者の健康や、ベトナムの電子電気機器廃棄物(e-waste)処理に従事する人々の健康調査も行っています。
さらに、アンケートの結果だけではなく、生体試料を測定して客観的な指標を用いたり、体の中で何が起きているのかを説明できる研究を目指しています。そのため、生体試料の分析を通じて、化学物質や生活環境が人の健康に与える影響を明らかにしようとしています。化学物質が実際に体の中にどのくらい取りこまれたかを探るバイオモニタリングや、血液や尿を用いたバイオマーカーの解析に加え、最近は生体分子全体を網羅的に解析するオミックス研究にも挑戦しようとしています。疾病の要因と結果に加え、疫学研究ではブラックボックスになる生体内のメカニズムを少しでも解き明かしたいと思っています。
研究にかける時間をどのように作り出すか
研究室を立ち上げられたのはいつ頃ですか
自分の研究室を持ったのは2021年度からです。それまでは北大の環境健康科学研究教育センターに所属し、複数の教員で大型プロジェクトを進めていました。学生の指導はその時から兼任という形で行っていましたが、あくまでもチームの一員という立場でした。2021年4月に保健科学研究院に異動して、初めて自分の研究室を主宰する形になり、学部生から大学院生まで指導する責任を担うようになりました。
実際に運営してみて、どのような難しさがありますか
一番の課題は体制づくりです。学部生は看護学専攻を担当しますが、看護専攻の学生は臨床実習が必須なため、どうしても研究にかけられる時間が限られます。就職活動や大学院入学試験もあるため、現実的には前期はなかなか卒業研究の時間が取れません。研究にかける時間をどのように作り出すかが悩みどころです。
疫学研究は調査によるデータ収集や実験室での測定に、データ解析が組み合わさっています。ゼミは留学生もいるので大学院生向けのものは英語で行っていますが、学部生には日本語の場も必要で、今までは二本立てで進めていました。これからは大学院生も学部生も同じ空間で学び合えるような環境になるよう、調整を進めています。今は研究室に学部生のデスクが無いので、自然に関わり合う仕組みをつくるのが難しいと感じていますが、学部生が研究を進める先輩と接することで、研究者になる姿をロールモデルとして身近に感じてもらいたいと思っています。
ご自身の学生時代との違いもありますか
私が学生の時の研究室は、先輩が後輩を見てくれる体制でした。学部生のときは東京理科大学から東京大学の研究室に派遣される形で研究をしていたのですが、修士や博士課程の先輩が学部生を直接指導してくれて、日常的に先輩とやり取りできる安心感がありました。今の研究室でも、そうした縦のつながりをどう作っていくかが課題です。また、大型の疫学研究は、チームでお互いにデータを創出していくことが必要になります。環境健康科学研究教育センターが進める出生コホートに一緒に携わっていくことで、調査によるデータ取得、生体試料の分析、統計解析によって関連を明らかにする、疫学研究の様々な側面を経験できることは大きな強みだと思っています。何より、協力しながら研究を進めることはとても楽しいです。
4年生は就職活動や大学院入試、実習、研究と本当に忙しいです。面接練習やエントリーシートの添削などはできる範囲でサポートしています。大学院に進むか迷っている学生には、じっくり話を聞いて一緒に考えるようにしています。研究指導にとどまらず、将来を見据えられるよう学生を支えることも大切だと思っています。それでも何より、「研究は楽しい」と思ってもらいたいと思います。

性別や国籍ではなく、その人が持っている力をどう伸ばすか
ダイバーシティやジェンダーについてはどのようにお考えですか
分野の特性もあるかもしれませんが、ありがたいことに、私はこれまで性別で不利益を感じたことはありませんでした。大学院時代の指導教員も女性の先生でしたし、環境健康科学研究教育センターや保健科学研究院も女性教員が比較的多いです。企業時代も女性の研究者が多い環境でした。研究室には留学生がいますが、性別や国籍ではなく、その人が持っている力をどう伸ばすかを重視しています。多様性を「違い」としてではなく「強み」として生かせる環境を作りたいと思っています。
PIとしての研究の進め方を間近で学んだことが大きな財産に
研究を続ける上で、ロールモデルとなる方はいらっしゃいましたか
自分の学位指導教員がロールモデルです。PIとして研究をどう進めていくかを間近で見て、本当に多くのことを学びました。まずはきちんと研究計画を立てることに加えて、環境疫学の研究では「正確に測る」ことが非常に大切です。どのように曝露を評価するのか、何をどう測定するのかを徹底して指導してくださいました。調査の中で血液や尿といった生体試料を集めて、研究費を獲得できれば後からさまざまな測定が可能になる。その重要性を教えていただいたのは大きな財産です。
また、製薬会社時代にも尊敬できる先輩や同僚に恵まれました。きめ細かく仕事に取り組む姿勢や、周囲をうまく巻き込みながら進めていく姿勢はとても印象的で、今でもその当時学んだことが研究プロジェクトを進めるうえでとても役立っています。上司もスタッフを生かしながら大きな仕事を進める方で、そうした姿を見て「自分もこうありたい」と強く思いました。

安心して暮らせる持続可能な社会につなげられるように
研究分野、社会への貢献について教えてください
持続的な地球環境を考える重要性が増しています。私の研究分野が社会に貢献できるのは、単にリスクを指摘するだけではなく、安全に暮らすための根拠を示すことです。統計的な関連を見つけるだけでなく、生体試料の分析を通して、体の中でどのようなメカニズムが働いているのかを解き明かす。それによって環境と健康のつながりを科学的に裏づけることが、分野への貢献になると考えています。
大量生産、大量消費社会で生み出される多くのものと、健康との関連を示して「これは危ない」と言うのは簡単ですが、現実には避けられないものも多いですよね。例えば、現在プラスチックに含まれる化学物質の健康リスク評価に取り組んでいますが、使い方を工夫して化学物質にさらされる量を減らせる方法があるはずです。「この程度であれば大丈夫」という基準を示すことは大切だと思います。また、要らないものは使わないことも重要です。科学的エビデンスを示すことで規制や基準作りに貢献することと、人々の生活に即した形の知見を届けることで、安心して暮らせる持続可能な社会につなげられるようにと思っています。
そのためには、論文として学術的に貢献していくことはもちろんですが、政策や規制など社会のルールを作る際にも役立てることのできるような結果として示していくことも重要だと考えています。
大学への貢献についてはどのようにお考えですか
北海道大学全体を見ると、女性研究者の数はまだ少ないのが現状です。大きな制度改革や女性の登用をすることももちろん大事ですが、私自身ができることは、まずは次に続く学生を育てることだと考えています。
大学院に進みたい、博士を取得したい、研究者を目指したい──そんな思いを持つ学生が、○○だから無理、と考えるのではなく、自分の希望を実現できる環境を整えること。それが結果的に大学全体の力を底上げする貢献になると思います。研究室を通じて次の世代が育っていくことが、私にできる最も大切な貢献だと考えています。

自分の強みとしてしっかりとした柱を立てつつ、周囲に広く意識を広げて
これから上位職を目指す人たちへメッセージをお願いします
自分の強みを活かしていってほしいと思います。どんな場面でも「私はこれができます」ということがとても大事だと思いますので、そういう力を身に着けて次のステップに進んでいっていただきたいと思います。
例えば、環境疫学や公衆衛生学はとても幅広い分野ですが、その中でも自分の能力や技術面でのアピールポイントがあると共同研究などに広がっていくと思います。
自分の強みとしてしっかりとした柱を立てつつ、周囲に広く意識を広げていくと新しいことにつながっていき、研究も発展していくのだと思います。
LILAS
Library
ノウハウ本はあまり読まないのですが、この本を手に取ったときに、自分の歩み方を肯定できたような気がしました。
多くの本は「目標を定めて、それに向かって努力する」ことを勧めますが、この本は少し違っていて、与えられた環境を受け入れ、流れに乗りながら進んでいく生き方の価値を教えてくれました。人生は思い通りにいかないことの方が多いと思います。けれども、計画どおりにならなくても、柔軟にそれを受け入れて、新しい波に乗れば、自分では考えてもみなかった世界が広がることもある。だからこそ、これからの時代をつくっていく若い方々には、そんな柔軟な姿勢と新しい発想を大切にしてほしいと願っています。これからの未来にたくさんの希望があることも、忘れないでいてほしいと思います。
LILAS
Plants
身の回りで多用される植物たち。長い歴史で繰り返し試されてきた植物たち。

-
セージ
学名:Salvia officinalis 科名・属名:シソ科アリギリ族
- 薬用サルビアとも言われる。観賞用にも料理にも使われる。
-
クレマチス
学名:Cymbopogon citratus 科名・属名:イネ科オガルカヤ族
- レモンのような香り、料理や精油、幅広い使われ方をされる。
-
トリカブト
学名:Thujopsis dolabrata 科名・属名:トリカブト族
- 根から花まで毒がある。毒は狩猟や薬用にも使われる。園芸種としても多様な種がある。
-
アスナロヒバ
学名:Thujopsis dolabrata 科名・属名:ヒノキ科アスナロ属
- 建築材、医薬品、化粧品、など幅広く使用される。
LILASは北海道大学創基150周年事業です。北海道大学は2026年に創基150周年を迎えます。