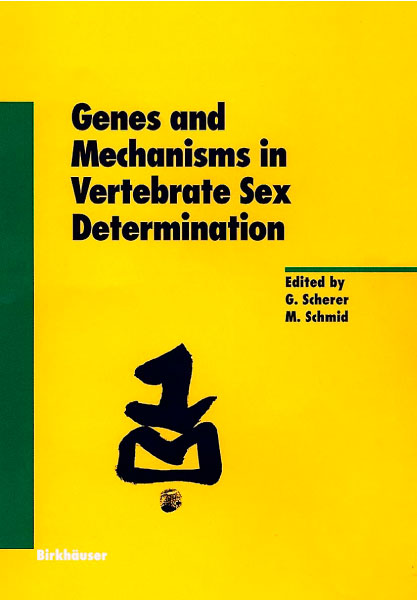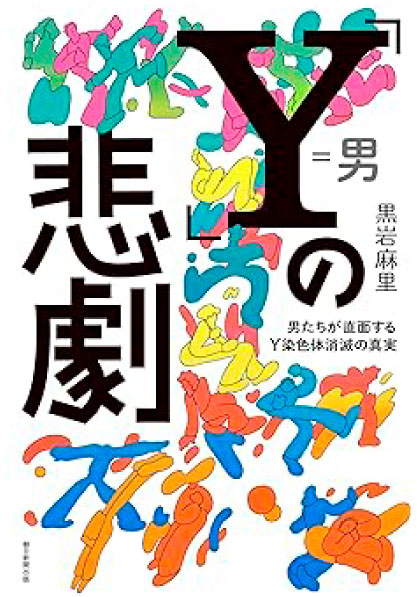03
- 黒岩 麻里先生
- 北海道大学理学研究院教授
途中で休んでも、誰かに頼っても、
決して研究をあきらめない
LILAS
Leaders for people with Innovation,
Liberty and AmbitionS.
フロントランナーとして活躍している女性リーダー(Leader)を紹介する女性研究者インタビューシリーズLILAS。リラはフランス語で札幌の花としても知られるライラック(Lilac)を意味します。 インタビューの内容から着想を得た植物のアレンジメントとともに、植物の持つ力強さやしなやかさ、多様性などのメッセージを媒介させながら、オリジナルインタビューシリーズとして発信していきます。
- 03
-
第三回は理学研究院の黒岩麻里さん。黒岩さんは哺乳類や鳥類を対象に性はどう決まるのか、という性決定について研究しています。子育て期に始まった研究者のキャリアは決して楽ではありませんでしたが、博士号取得時に女性研究者からかけられた言葉を胸にここまで研究を続けてきたといいます。学内業務にも積極的に関わることで北大をもっと良くしていきたいと話します。

研究面では独自性を、教育面では自律性を
研究室運営をされているなかで、研究と運営の両立をする工夫や苦労はありますか?
子供が二人おり、今はもう大きくなったので少しは楽になりましたが、小さい頃は大変でした。学位取得後すぐに講師になり、学生の教育を始めましたが、当時子供が疾患を持っており、10年ほど入退院を繰り返していたので。
研究面ではオリジナリティを追求し、研究のトレンドを追いかけず、自分のペースで進められる研究をポリシーとして進めました。
教育面に関しては、学生が研究室に入る前に私の状況を伝え、自立心をもって研究に取り組む必要があることを伝えた上で、納得して研究室を選んでもらいました。もちろん研究面も教育面も理想通りにはいかないこともあり、競争相手が現れることもあったり、指導方針について悩むこともありました。
教授もスタッフも状況を理解してくれていて、私がいないときは学生の相談にのっていただいたときもありました。周囲のサポートや理解は大きかったです。
その日にやることを決め、とにかくテキパキと進める
時間のやりくりについて工夫されていたことはありますか?
子供の保育園へのお迎えが午後6時までだったので、午後5時半前には研究室を出なければいけませんでした。夫が家事をしてくれたりお迎えにいってくれたり、夫婦で分担はしていましたが、基本的には毎日午後5時までに、その日のタスクは終えるように意識をしていました。子供が大きくなった今もそのスタイルは変えておらず、今は私が帰らないと学生は帰りにくいのでそうしています。
私が得意なのは、頭の切り替えを早くすることです。とにかく早く切り替えて、時間内に様々な仕事を終わらせていました。
でも、これはあまり良いことではないかもしれません。時間を決めているから余裕がありません。研究や教育は余裕があって、無駄に思える時間があるときにこそ人間関係が築かれたり、良い発想が生まれます。無駄話や移動時間での立ち話で信頼関係が生まれて仕事がしやすくなったり、ふとした瞬間に新しい発想が生まれたりします。学生のサポートについては、学生の集中力が続くように、実験の話や研究の話は短時間で済むように心がけています。一方、研究面以外の将来の話など、学生が不安に思っていることなどは、長く時間をかけて話をすることをこころがけており、メンタルのサポートも重視しています。
今は助教2人とポスドクもいるので、私の他にも相談する相手がいることでうまく回っている一面もあります。

女性は研究を途中で中断するライフイベントが多い。中断してもいいが、どんなに時間がかかってもいいから、必ずリスタートしてほしい。
ロールモデルのような存在はいますか
博士号を取るまで所属していた、名古屋大学大学院生命農学研究科の束村博子先生(2024年3月まで副総長/男女共同参画・多様性担当)です。男女共同参画の活動を長くされていて、心の支えになった方です。束村先生とは分野が異なるので、研究のつながりはありませんが、私の学位授与式の後、懇談会で話しかけてくださって、「最近女性で学位を取った人が少ないから、期待しているし、頑張ってほしい」と励まされました。「女性は研究を途中で中断するライフイベントが多い。中断してもいいが、やめることは絶対にしないで。どんなに時間がかかってもいいから、必ずリスタートしてほしい」と言われ、絶対にやめないと心に誓いました。
息子が入院し、研究活動が中断した際には、研究を続けることができなくなるかもしれないと不安に思ったこともありましたが、束村先生の言葉を思い出しました。
研究面でのロールモデルは、メアリー・ライオン先生です。哺乳類のX染色体不活化現象を発見した有名な方で、亡くなったときはネイチャーに追悼記事が載ったほどです。
また、もう一人はオーストラリアのジェニファー・グレイブス先生です。性染色体の進化研究の大家で、80代の今もなお現役教授として活躍されています。学生時代は憧れの存在でした。今は私も研究者として一定の成果を上げることができ、研究の相談をしたり、ワインを一緒に飲んだりなどの交流もある存在になりました。
研究面でのモデルは海外の研究者ということですが、やはり日本の女性研究者は少ないですか
少ないと思います。海外の研究者から、日本の女性研究者の少なさを指摘されるほどです。海外では日本のジェンダー不平等は有名で、アジアのなかでも劣っている状況です。日本では、大学生の性比の偏りも問題になっています。
男女にかかわらず、博士課程の学生を育てるうえで重要視していることは、業績をたくさん積めるようにすることです。私は指導教員の先生から、私が女性だからということと関係なく、とにかく論文を出すようにと言ってもらいました。論文の出し方については、色々な考え方があります。質を重視する研究者もいれば、質より量(数)を重視する研究者もいます。私の指導教員はどちらかというと後者の考え方で、どんなに小さなデータでも、論文として発表しなければ意味がない、と常々おっしゃっていました。私も学生を指導する上では同じスタンスを取っています。また、学会などでの発表のチャンスを、できるだけ与えるようにしています。
一番の野望は自分の研究が教科書に載ること
大学教員としての大学組織や研究分野の貢献について伺えますでしょうか
7年前から本学の総長補佐として、広報・社会連携を担当しています。また、2026年に北海道大学は創基150周年を迎えるのですが、その記念事業企画運営委員会を担当しています。総長補佐に就いたのは、教授に着任して間もない頃でしたので、当初は戸惑いもありました。ですが、若い世代かつ女性が大学運営にかかわることは大事なことだと思い、自分のミッションだと思って続けてきました。
ずっと北大で研究を続けてきて、愛着もありますし、北大を少しでも良くしていきたい、そのために大学運営に関わりたい、貢献したいと思い続けています。
研究面での一番の野望は、自分の研究が教科書に載ることです。
私の研究が他大学の入試問題になったり、講義の題材にしていただいたりして、この野望はだんだんと現実になりつつあります。高校の教科書や他国の書籍で紹介され、世界の人が、北大の黒岩を知ってくれることで北大の名を世界により広めたいと考えています。
自分の研究が国内外で広く知られるようになってきたという実感は、10年ほど前から少しずつありました。国内では、テレビや新聞にとりあげられることがしばしばあります。ただし、メディアに出ることと学術的に評価されることとは別だと思っています。本当の意味で研究者が成果を上げるには、世界的に認知されなければいけないと思っています。
2年前に哺乳類の新しい性決定メカニズムを世界で初めて発見するという、自分でも満足できる成果がでて、本学からの英文プレスリリースなどを経て、海外でも広く記事になりました。その際は、海外の著名な研究者から、発表を祝福するメッセージが直接届いたり、英語圏以外の国・地域でも多くの記事になりました。
国際学会でオーストラリアを訪れた時に、演題受付で研究タイトルを伝えたら「あなたの研究、知っていますよ。ニュースになり、オーストラリアでも有名ですよ」と言われました。その方は学会運営を受託しているイベント会社の社員で、研究者ではなかったのですが、一般の方にも知っていただけているということに驚くとともに、私の研究が世界的に広く知られていることを実感しました。
研究への貢献として、海外とのネットワークも重要視しています。私は留学経験がなく英語が苦手なのですが、海外の著名な研究者に連絡をとって日本に招待したり、学会では自分から話しかけてコミュニケーションをとったりと、ネットワークを作る機会を増やすように努力しました。学生には留学を勧めていますし、研究室には留学生もいますので、外国人学生との交流もはかっています。学生たちには世界に目をむけるように言っていますが、今は円安の影響で、国際学会への参加が経済的な理由により以前よりも難しくなっており、国際雑誌への投稿料も高く論文を出すこともままなりません。
現在、日本の科学研究費増額要請の運動が行われていますが、このままでは日本の科学研究はだめになると感じています。給料の良い海外のポストにつき、優秀な人材は国外に流れてしまっています。
私自身は日本でしかできない研究テーマを扱い、日本じゃないとできない強みを持つように意識しています。そして、日本の科学研究に貢献したいと考えています。
社会貢献として活動されていることはどんなことでしょうか
社会への貢献については、私の研究は「性」に関するテーマなので、一般の人の関心が高く、興味を持ちやすいと思っています。多くの人に研究を知ってもらい、生命科学分野に興味をもってもらい、性の多様性を知ってもらえるよう意識しています。
私の著書は、タイトルも帯も出版社が考えてくれています。一般の方に手に取ってもらえるように、少々ショッキングなキャッチコピーがついたりもしていますが、一番伝えたい内容は性の多様性についてです。このことについて、より多くの読者の方々に伝わっているといいなと思っています。
今年(2024/5)出版した新しい著書「「Y」の悲劇 男たちが直面するY染色体消滅の真実」は一般書なので、わかりやすさを心掛けつつも、最先端の研究を盛り込みました。また、しっかりとエビデンスをつけるために丁寧に引用をつけたため、結局出版まで3年かかりました。
担当編集者の方が大変熱心で、自作のPOPを持って書店回りをしてくれたりしています。研究も教育も執筆も、人とのつながりが楽しいです。私自身はどちらかというと人見知りなのですが、どの活動においても人とのつながりを大切にしています。

大変な時は誰かに頼り、決して研究をやめない
これから上位職を目指す研究者の人たちへメッセージをお願いします
途中で休んでもいいから、粘り強く続けてほしいです。やめることは絶対しないでほしいと思います。ポジションによってできることは変わるかもしれませんが、どういうかたちであれ、絶対にやめないでほしいです。
大変な時は誰かに頼ってください。時として環境が整っていないのに職位だけがあがり、仕事のみ増えていくような状況もあるかもしれません。大変な時はとにかく頼ってほしいです。近くに頼る相手がいなかったら、DEI推進本部やそこに兼務している北大の教員(男女問わず)などに相談してほしいです。直接的な解決に繋がらなくても、相談したことで気持ちが軽くなったり前に進むことができます。私にもそういう経験がありました。DEI推進本部では女性研究者のネットワークを大切にしているので、ぜひ交流の輪を広げてほしいです。
LILAS
Library
LILAS
Plant
今まで当たり前だったことがそうでなかったこと。スカシユリの蕾とハマナスの花びら、ブドウとナデシコとありえない、もしくはそう思われる組み合わせで構成。

-
スカシユリ
学名:Lilium maculatum Thunb 科名・属名:ユリ科ユリ属
- 北大構内ではオオウバユリが咲くのを見ることができる。
-
ナデシコ
学名:Dianthus 科名・属名:ナデシコ科ナデシコ属
- 品種多く北海道に自生する。
-
ハマナス
学名:Rosa rugosa 科名・属名:バラ科バラ属
- 耐寒性強く海岸に多く自生する。バラの原種。
-
ブドウ
学名:Vitis 科名・属名:ブドウ科
- 写真のブドウの属は不明。先祖返りしたかノブドウと交雑したとみられる。
LILASは北海道大学創基150周年事業です。北海道大学は2026年に創基150周年を迎えます。